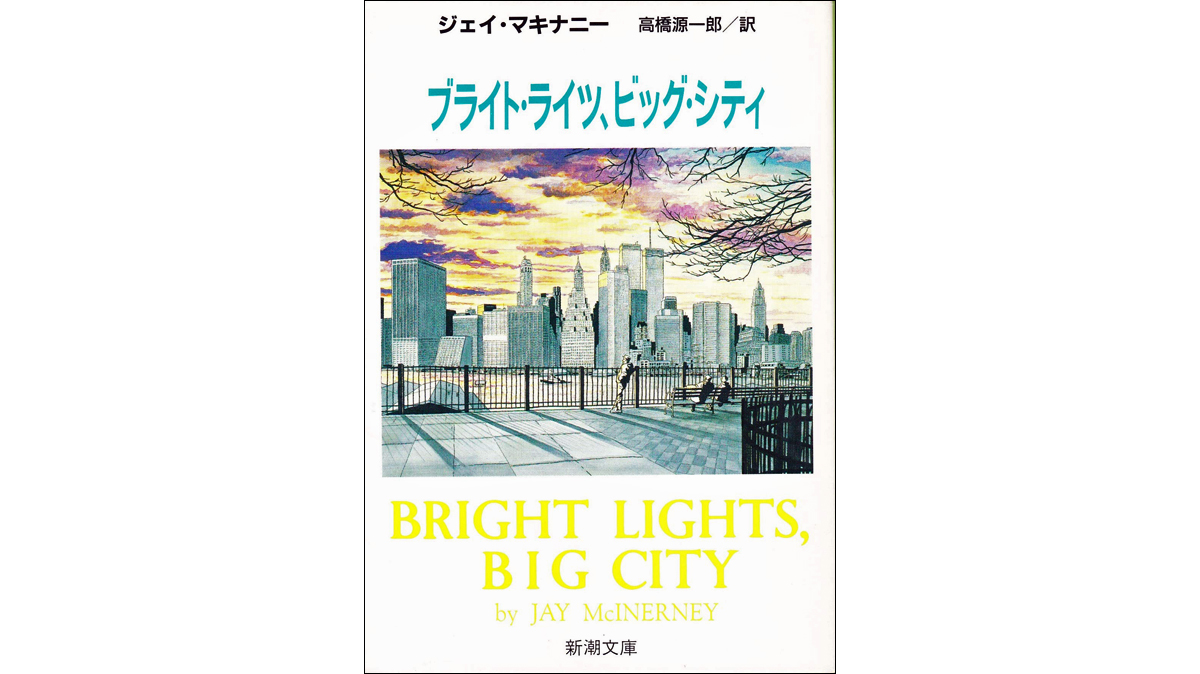新潮文庫に「ブライト・ライツ、ビッグ・シティ」というのがあったのだけれど、これが今は品切れなのか絶版なのか、新品は手に入らないとわかった。とても残念に思う。
約10年前、同僚が読んでいたこの本がなぜか面白そうで、早速自分も書店で買って読み始めた。
なぜ面白そうに思ったのか、今ではまったく思い出せない。書名に引かれたとは言えない。表紙もきれいだけれど、すごい表紙というわけでもない。恐らくはその同僚が、強烈に薦めてくれたのだろう。
ともあれ、実際に読み始めたら止まらなくなった。何が何でも、早く最後まで読まなくてはならないと思わされた。
僕自身のことが書いてあったからだ。
舞台はニューヨーク。主人公は一流出版社に勤めながら、毎晩ナイトクラブに通っていて、コカイン中毒。このプロフィールが僕と同じだったという意味ではない。すみかも、職場も、遊び方も、全然違う。
ブラック・マンデー前のニューヨークと、バブル崩壊前の東京をダブらせることはできるかも知れないけれど、それもあまり重要なことではない。
文章は終始、二人称で書かれる。
普通、小説は三人称でしょう。「彼は、午前六時にナイトクラブにいるような男ではなかった」とか。あるいは、最近は一人称の小説が多いから、「俺は、夜明けのこんな時間に、こんな場所にいるような男ではない。本当は」とか。
ところがこの小説は、二人称で書かれている。「きみはそんな男ではない。/夜明けのこんな時間に、こんな場所にいるような男ではない」が書き出しだ。
「きみ」とやられて、この小説が僕自身のことを書いたものだと思わされたのか? そういう面もなくはないと思うけれども、それがすべてでもない。
なぜか、どういうわけか、この小説には「僕自身のことが書いてある」と思わせる力がある。きっと僕以外の人にとっても。
たぶん、自分の本来の希望とか理想とか、そういうものとズレたところに今の自分がいて、「ああ、なるほどねー。なんかこうやって人生って終わっていくものなのねー。ふーん……」なんてことを早20代で思うハメに陥っている辺り。誰もが一度や二度は(あるいはもっと)思うそんな辺り。そこら辺を突いて来る力なのだろうなと思う。
これを読み終わった3カ月後、僕は会社を辞めた。その決断の理由はこの本を読んだことだった、とまでは言わないけれど、この本との出会いは、人生の中での大きな伏線の一つだったと思う。
今でも時々、この本を薦めてくれた元同僚と「そうだね」と話す。彼は僕より1月前に退社した。
この本のラストシーンを読み返すたびに涙が止まらない。仕事に行き詰るたび、この本のラストシーンだけ開いて読み返し、声を上げて泣いてたっぷり眠る。――よく効くストレス解消法の一つです。